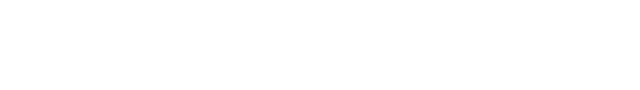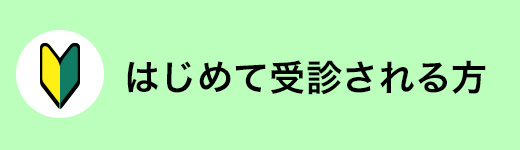片頭痛・緊張型頭痛・群発頭痛
【概念】
片頭痛は、拍動性の頭痛発作を繰り返す原発性頭痛疾患です1。三叉神経血管説により、脳血管の拡張と神経ペプチド(CGRP:カルシトニン遺伝子関連ペプチド)の放出が関与すると考えられています。緊張型頭痛は、頭部周囲の筋肉の持続的収縮により生じる非拍動性の頭痛です1。群発頭痛は、一側性の激烈な頭痛と同側の自律神経症状を特徴とする三叉神経・自律神経性頭痛の代表的疾患です2。
【頻度】
片頭痛の有病率は日本では男性3.6%、女性12.9%とされ、20-40歳代の女性に多く認められます1。緊張型頭痛は最も頻度の高い原発性頭痛で、有病率は約22%です1。群発頭痛の有病率は0.1-0.5%と稀で、男性に多く(男女比3-4:1)、20-40歳代に好発します2。
【症状】
片頭痛は、4-72時間持続する拍動性頭痛で、中等度から重度の痛みを特徴とします。悪心・嘔吐、光過敏・音過敏を伴い、日常動作により増悪します1。約30%の患者で前兆(主に視覚症状)を認めます。緊張型頭痛は、頭部の圧迫感や締め付け感として表現される非拍動性の頭痛で、軽度から中等度の痛みが特徴です1。群発頭痛は、一側の眼窩部・眼窩上部・側頭部の激烈な痛みが15分-3時間持続し、同側の結膜充血、流涙、鼻閉、鼻汁、縮瞳・眼瞼下垂を伴います2。
【検査】
頭痛診断は主に病歴聴取と身体診察によりますが、国際頭痛分類第3版(ICHD-3)の診断基準を用いて行います1。二次性頭痛を除外するため、警告徴候(突然発症、発熱、項部硬直、神経学的異常など)がある場合は、CT・MRI検査を実施します1。群発頭痛では、MRI検査で下垂体腫瘍など器質的疾患の除外が重要です2。
【治療】
片頭痛の急性期治療には、トリプタン系薬剤(スマトリプタンなど)が第一選択薬です1。2021年より新規薬剤ラスミディタンも使用可能となりました。予防療法には、β遮断薬(プロプラノロール)、Ca拮抗薬(ロメリジン)、抗てんかん薬(バルプロ酸、トピラマート)を用います1。CGRP関連薬物(エレヌマブ、ガルカネズマブ)も2021年より使用開始されています3。緊張型頭痛には、アセトアミノフェンやNSAIDsによる対症療法と、筋弛緩薬、三環系抗うつ薬による予防療法を行います1。群発頭痛の急性期治療にはスマトリプタン皮下注射、高濃度酸素吸入が有効です2。予防療法にはベラパミル、リチウム製剤を使用します2。
- 頭痛の診療ガイドライン作成委員会. 頭痛の診療ガイドライン2021. 医学書院, 2021.
- Petersen AS, Lund N, Goadsby PJ, Belin AC. Recent advances in diagnosing, managing, and understanding the pathophysiology of cluster headache. Lancet Neurol. 2024;23(4):390-402.
- San-Juan D, Velez-Jimenez K, Hoffmann J, et al. Cluster headache: an update on clinical features, epidemiology, pathophysiology, diagnosis, and treatment. Front Pain Res. 2024;5:1373528.