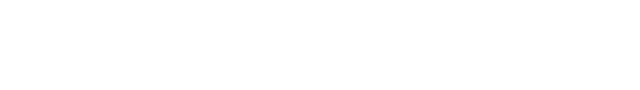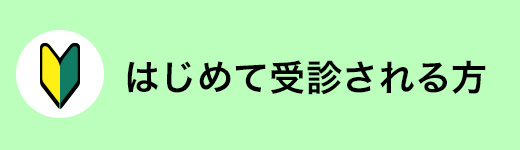ギラン・バレー症候群
【概念】
ギランバレー症候群(GBS)は、感染後に発症する急性炎症性脱髄性多発神経根ニューロパチーです¹。病理学的には、急性炎症性脱髄性多発神経根ニューロパチー(AIDP)、急性運動軸索ニューロパチー(AMAN)、急性運動感覚軸索ニューロパチー(AMSAN)に分類されます。分子相同説により、先行感染に対する抗体が末梢神経のガングリオシドと交差反応することで発症すると考えられています¹。
【頻度】
GBSの発症率は年間人口10万人当たり1-2人とされています¹。男女比は約1.5:1で男性にやや多く、全年齢層で発症しますが50-60歳代に多い傾向があります。日本ではAMAN型の頻度が欧米より高いとされています¹。
【症状】
急性に進行する対称性の四肢筋力低下と腱反射消失が特徴的です。症状は下肢から上肢へと上行性に進行し、重症例では呼吸筋麻痺、嚥下障害を来します。感覚障害は軽微で、手袋靴下型の感覚鈍麻程度のことが多いとされています¹。自律神経障害として、血圧変動、不整脈、消化管運動障害を認めることがあります。Miller Fisher症候群では外眼筋麻痺、運動失調、腱反射消失の三徴を呈します¹。
【検査】
診断は臨床症状と電気生理学的検査、髄液検査により行います¹。神経伝導検査では、AIDP型では伝導ブロック、伝導速度低下、遠位潜時延長を認め、AMAN/AMSAN型では複合筋活動電位振幅の低下を認めます¹。髄液検査では細胞数正常でタンパク質増加(albumino-cytological dissociation)を認めます。抗ガングリオシド抗体(抗GM1、GD1a、GQ1b抗体など)の測定も診断に有用です¹。2024年の最新研究では、自己反応性T細胞の末梢神経への直接的な関与が明らかになりました2。
【治療】
免疫グロブリン大量静注療法(IVIg:0.4g/kg/日×5日間)または血漿交換療法が標準治療です¹。両者の有効性は同等とされ、発症2週間以内の開始が推奨されます3。副腎皮質ステロイドの単独使用は有効性が認められていません¹。呼吸筋麻痺に対しては人工呼吸管理を行います。リハビリテーションは急性期から開始し、筋力回復を促進します¹。重症例に対するセカンドラインIVIg療法の効果は限定的であることが2021年の臨床試験で示されています⁴。2024年現在、補体阻害薬(エクリズマブ)の効果について研究が進行中です2。
- ギラン・バレー症候群診療ガイドライン作成委員会. ギラン・バレー症候群診療ガイドライン. 南江堂, 2013.
- Leonhard SE, Papri N, Querol L, et al. Guillain–Barré syndrome. Nat Rev Dis Primers. 2024;10(1):84.
- Hughes RA, Swan AV, van Doorn PA. Intravenous immunoglobulin for Guillain-Barre syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2014;2014(9):CD002063.
- Walgaard C, Lingsma HF, Ruts L, et al. Second intravenous immunoglobulin dose in patients with Guillain-Barre syndrome with poor prognosis (SID-GBS): a double-blind, randomised, placebo-controlled trial. Lancet Neurol. 2021;20(4):275-283.