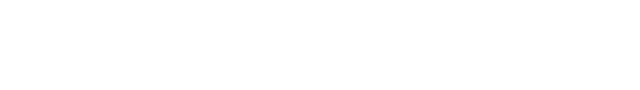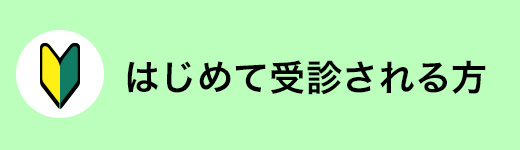てんかん
【概念】
てんかんは、脳の神経細胞の異常な電気的放電により、反復性の発作を特徴とする慢性の脳疾患です1。国際抗てんかん連盟(ILAE)の定義では、24時間以上の間隔をおいて2回以上の非誘発性発作が起こった場合、または1回の非誘発性発作があり今後10年間の再発リスクが60%以上の場合にてんかんと診断されます1。
【頻度】
てんかんの有病率は約0.5-1%で、生涯有病率は約3%とされています1。発症は二峰性を示し、小児期と高齢期に多く認められます。新規発症率は年間約50/10万人で、高齢化社会に伴い高齢発症てんかんの増加が問題となっています1。
【症状】
発作型は2017年ILAE分類により、焦点発作、全般発作、起始不明発作に分類されます1。焦点発作は脳の限局した部位から開始し、意識減損の有無により焦点意識保持発作と焦点意識減損発作に分けられます。全般発作は両側大脳半球に広く電気的放電が及ぶもので、強直間代発作、欠神発作、ミオクロニー発作、脱力発作などがあります1。発作間欠期には認知機能障害、精神症状、社会適応の問題を生じることがあります²。
【検査】
診断の基本は詳細な病歴聴取と目撃証言です1。脳波検査はてんかん診断の基本的検査で、発作間欠期脳波でてんかん性放電を検出します。長時間脳波記録、ビデオ脳波モニタリングにより発作の記録を行います1。MRIでは器質的病変の検索を行い、海馬硬化症、皮質異形成、腫瘍などを評価します。SPECT、PETでは発作焦点の同定に有用です1。2024年の最新技術として、機械学習を用いた脳波解析やMRI画像解析の応用が進んでいます³。
【治療】
抗てんかん薬による薬物療法が基本となります1。第一選択薬として、焦点発作にはカルバマゼピン、レベチラセタム、ラモトリギンなどを、全般発作にはバルプロ酸、レベチラセタムなどを用います1。薬剤抵抗性てんかんに対しては、てんかん外科手術(側頭葉切除術、病変切除術など)、迷走神経刺激療法(VNS)、ケトン食療法を検討します1。2024年現在、新規抗てんかん薬(ペランパネル、ラコサミドなど)の適応拡大や、脳深部刺激療法(DBS)の応用が進んでいます³。精神的・社会的サポートも重要で、患者・家族への教育、就労支援、運転免許に関する指導なども必要です⁴。
- てんかん診療ガイドライン作成委員会. てんかん診療ガイドライン2018. 医学書院, 2018.
- Valente KD, Reilly C, Carvalho RM, et al. Consensus-based recommendations for the diagnosis and treatment of anxiety and depression in children and adolescents with epilepsy: a report from the psychiatric issues task force of the ILAE. Epilepsia. 2024;65(11):3142-3165.
- Rehab N, Siwar Y, Mourad Z. Machine Learning for Epilepsy: A Comprehensive Exploration of Novel EEG and MRI Techniques for Seizure Diagnosis. J Med Biol Eng. 2024;44(4):523-542.
- Pellinen J, Foster EC, Wilmshurst JM, et al. Improving epilepsy diagnosis across the lifespan: approaches and innovations. Lancet Neurol. 2024;23(5):456-468.