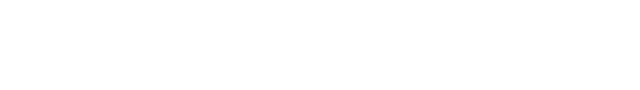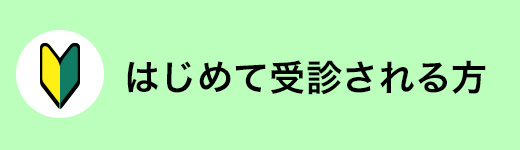三叉神経痛
【概念】三叉神経痛(さんさしんけいつう)とは、顔の感覚を司る三叉神経の異常により生じる強烈な顔面痛です。「顔面の電気ショック」とも表現される、非常に特徴的な痛みが現れます。
三叉神経痛は 国際頭痛分類第3版(ICHD-3)¹ において「一次性頭痛」の一つとして分類されており、頭痛そのものが病気である疾患群に含まれています。
最新の研究では、三叉神経痛の病態として以下のメカニズムが解明されています:
・三叉神経根部での血管による圧迫(血管神経圧迫説)
・炎症性サイトカイン(IL-1β、IL-6、TNF-α)²の異常増加
・TRPV1チャネルやCGRP(カルシトニン遺伝子関連ペプチド)²の関与
・GABA作動性抑制シグナル²の減弱による中枢神経の過敏化
これらの複合的なメカニズムにより、通常は痛みを感じない軽い刺激でも激痛が引き起こされる「アロディニア」という現象が生じます。
【症状】
三叉神経痛の症状は非常に特徴的で、ICHD-3の診断基準¹に以下のように定められています:
*痛みの性質
突然発症し、通常は数秒から2分間持続
鋭い、刺すような、電気ショック様または切るような痛み
高度の強さ
一側性(片側のみ)
*痛みの分布
・三叉神経の分布領域(頬、あご、額)に沿って現れる
・第2枝(上顎神経)、第3枝(下顎神経)の領域に多い
・誘発因子(トリガー) 三叉神経痛の大きな特徴は、日常の軽微な刺激で激痛が誘発されることです:顔を洗う、歯を磨く、話をする、食事をする、冷たい風を受ける、ひげを剃るなど。
*その他の症状
最新の研究では、以下の症状も報告されています²:
・感覚異常(感覚低下、しびれ、一部では感覚過敏)
・睡眠障害
・精神的ストレス(痛みへの恐怖から日常生活が制限される)
【検査】
三叉神経痛は「臨床診断」が基本となります。つまり、特徴的な症状と経過から診断され、神経学的検査では異常が見られない¹ことが診断基準の一つです。
*詳細な病歴聴取と身体診察
・痛みの性質、持続時間、分布の確認
・誘発因子の特定
・神経学的検査(感覚・反射の評価)
【画像検査】
MRI:血管神経圧迫の確認、脳腫瘍などの除外
MRA(MR血管撮影):血管構造の評価 最新の研究では、「三叉神経橋徴候」²と呼ばれるMRI所見も注目されています
【神経生理学的検査】
瞬目反射検査²:三叉神経の機能評価
感覚神経伝導検査
【鑑別診断】
非定型三叉神経痛、三叉神経・自律神経性頭痛、歯科疾患、副鼻腔炎、帯状疱疹後神経痛
【治療】
*薬物療法
・カルバマゼピン³が三叉神経痛の第一選択薬として確立されています:用量200~1,200mg/日、有効率:約70-80、作用機序:神経の過剰な興奮を抑制
※最新の神経障害性疼痛薬物療法ガイドライン⁴では、以下の薬剤も推奨されています:
・ガバペンチン²:用量1,800~3,600mg/日
三叉神経痛以外の神経障害性疼痛にも有効
・プレガバリン²:用量300~600mg/日
ガバペンチンより忍容性が良好
疼痛と睡眠の改善が報告されている
・ミロガバリン²:15~30mg/日(疼痛スコアの有意な低下を報告)
※その他の薬剤
オキシカルバゼピン、ラモトリギン、バクロフェン、局所治療、リドカイン5%パッチ²、カプサイシン8%パッチ²
【介入的治療】
薬物療法が無効な場合、以下の治療が検討されます:
・ボツリヌストキシンA注射²:用量25~200単位/セッション
8~12週毎の施行。複数の研究で疼痛スコアの有意な低下を確認
・神経ブロック
上眼窩神経ブロック
下眼窩神経ブロック
オトガイ神経ブロック
高周波熱凝固術⁵
・パルス高周波法:長期的な疼痛緩和が期待できる
・脊髄刺激療法²:頭頸部の慢性疼痛に対する治療。70%以上の患者で有意な緩和を報告
【外科的治療】
・微小血管減圧術:三叉神経根部の血管圧迫を解除。根治的治療として期待される
・ガンマナイフ治療:低侵襲な放射線治療。高齢者や手術リスクの高い患者に適応
【予後】
薬物療法:「いかなる薬剤でも痛みが50%以上軽減する有意効果は50%未満の患者にとどまる」²ため、複数薬剤の併用がしばしば必要
介入的治療:ボツリヌストキシン注射で12週間の効果持続を確認²
外科的治療:微小血管減圧術で約85-95%の患者が痛みの改善を得られる
・薬物中断後の再発率は高い
・定期的な医学的管理が重要
・生活の質への影響
適切な治療により日常生活の大幅な改善が期待できる
精神的サポート²も重要(認知行動療法の併用)
【予防的管理】
帯状疱疹関連の三叉神経痛では、**帯状疱疹ワクチン(Shingrix)**²による予防効果(有効率76-88%)が確認されている
【今後の展望】
病態生理の理解深化に基づく新規治療標的の開発²が進められており、より個別化された治療戦略の確立が期待されています。
【引用文献】
1 日本頭痛学会・国際頭痛分類委員会(訳):国際頭痛分類第3版(ICHD-3)日本語版. 2019
2 Niemeyer CS, Harlander-Locke M, Bubak AN, et al. Trigeminal postherpetic neuralgia: from pathophysiology to treatment. Current Pain and Headache Reports. 2024;28:26
3 日本ペインクリニック学会:慢性疼痛治療ガイドライン. 2018
4 日本ペインクリニック学会:神経障害性疼痛薬物療法ガイドライン改訂第2版. 2016
福井聖,丹羽英美:パルス高周波法の最新治療―最新機器,パラメーターを用いた治療法とメカニズム―. 日本ペインクリニック学会誌. 2025;32(5)
※本記事は最新の医学論文に基づいて作成されていますが、個々の症状や治療については必ず専門医にご相談ください。